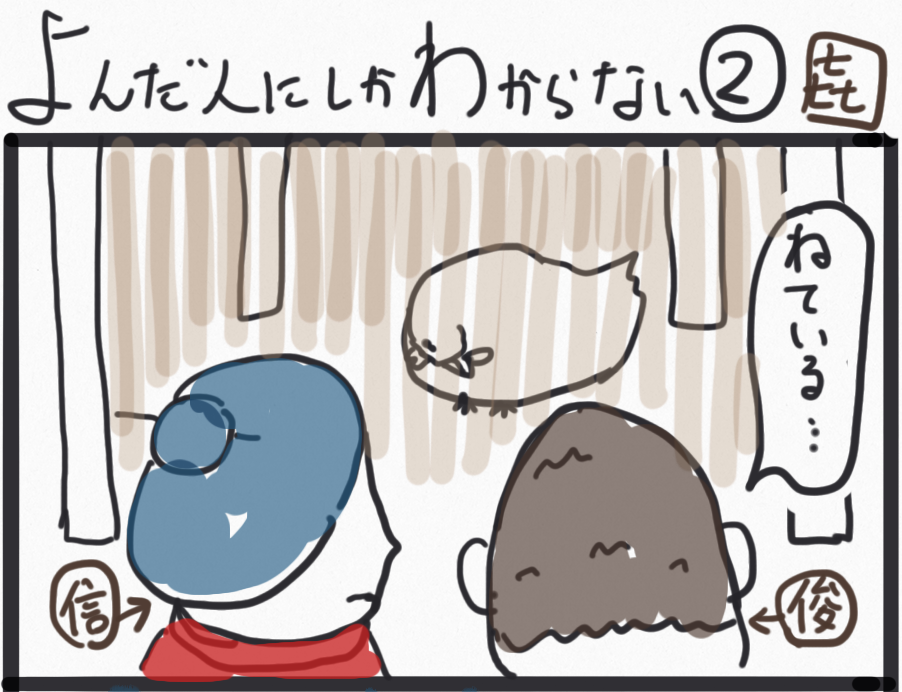今回コラムを担当してくれるのは、劇団ののに舞台時代から参加してくれている、田島裕人(たじまゆうと)氏です。

普段はおとなしく無口な田島君ですが、自分の好きなものの話になると突然、熱を込めて喋り出します。
そんな彼が今回ハマったのは、2019年末に放送されたNHKスペシャルドラマ「STRANGER 〜上海の芥川龍之介〜』です。
芥川龍之介が今から100年ほど前の1921年に上海に大阪毎日新聞社の特派員として滞在した際の手記をもとに作られたドラマで、主演・松田龍平さん、脚本・渡辺あやさん(朝の連続テレビ小説「カーネーション」などを担当)という豪華っぷり。
田島君はこの作品を観てからというもの、関連書籍を読み込み、ドラマを何度も見直し、シーンごとの関連をExcelにまでまとめるほどの熱中ぶりです。それはもはや、狂気の域です。

ドラマを、7つのキーワードから様々に考察する、全3回の大型コラム企画となっております! 静かな興奮(狂気)が伝わってくる文章を、お楽しみください。(第一回からもう論文の序論みたいになってるし、怖いよ、ぶるぶる)
※以下、ドラマのネタバレ注意!
はじめに(概要)
本コラムは、2019年末に放送されたNHKスペシャルドラマ「STRANGER ~上海の芥川龍之介~』について偏愛的に考察した文章です。
うっかり足を踏み入れると、非常にディープな世界に迷い込んでしまう可能性があります。
このドラマは、どんでん返しやド派手なアクション等、刺激や興奮を求めるような作品ではありませんので、こんなに考察したりすること自体、たいへんな物好きだということは自覚しております。
ちなみにこの作品、いつ再放送されるかも分からない作品なので、ネタバレも一切気にせず、容赦なく、このドラマの世界に引きずり込ませていただきます!
主人公 芥川龍之介とは
さて、早速にはなりますが、「芥川龍之介」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。
学生時代に読んだ「羅生門」でしょうか。それとも「鼻」や「蜜柑」でしょうか。
作品は覚えていないよ、という方でも、この写真であれば存じでしょう。

端正な顔立ちの中の鋭いまなざし、尖った顎や手元が知性を感じさせる写真です。「いかにも文豪」といったたたずまいです。
ちなみに、この写真が撮影されたのは、今回の作品の背景となる上海旅行直前にあたる1920年頃で、当時28歳の肖像とのことです。
……若いですね。
この頃には既に「羅生門」、以前劇団ののでも取り上げた「鼻」「蜜柑」「蜘蛛の糸」などの作品を発表しており、気鋭の作家という位置づけを確立していました。
当時のエリートコースである一高(いちこう)→東京帝大を卒業し、在学中から雑誌に小説を寄稿。そのまま作家として注目を集めた、王道中の王道。華麗な経歴です。
芥川の自殺の理由に深く関係あるドラマ
さて、そんな芥川ですが、みなさんご存じの通り、齢35にして自殺しています。
そしてその自殺の理由を「将来に対する唯ぼんやりとした不安」と記しています。実に抽象的なこの理由を見て、「文豪の死の理由には相応しいのかも……!」と一瞬雰囲気に騙されかけますが、少し冷静に考えてみると、「唯ぼんやりとした不安……? 人間ってぼんやりとした不安を理由に死んでしまっていいんですか、芥川先生……?」と不思議に思ってしまいます。
芥川が生きたのは明治、大正、昭和とまたがる時代です。日本は明治維新後の産業革命を経て戦争へと向かっていった時期。日清・日露戦争にも勝ち、上り調子の日本は活況でした。それにもかかわらず、太平洋戦争を前に自殺するような理由はどこにあったのか。
その理由を、このドラマでは物語の形式をとり、一説を提示しています。
今回、ドラマの舞台となったのは、芥川が大阪毎日新聞社の特派員として1921年に訪れた中国、上海です。
「清王朝が倒れ、共産党政権が成立する前夜、東アジアへの支配を強めていた西欧列強諸国の拠点を抱え混沌としていた上海を、日本の文豪はどう見つめたのか」という点が、このドラマの中心テーマとなっています。
いよいよコラムが始まるよ!
本コラムでは、上海旅行に関する作品群および時代背景と、芥川龍之介の “人となり”、物語に一本の縦筋をもたらすオリジナルストーリーが、どのように組み合わさっているのかを見ていくこととなります。
芥川龍之介は、当時の中国・上海をどう眺めたのか、どのように旅行前後の作品と関わっているのか、また、オリジナルストーリーを加えた作品全体はどのように見ることができるのか、などを考え、いつ再放送されるかも分からないスペシャルドラマに対して、熱量をぶつけてまいります。
……そうです、これはとてもクレイジーな企画なのです。
さて、それでは、「STRANGER~上海の芥川龍之介~」(以下「STRANGER」)についてのコラム、次のトピックから、本格的にスタートです。
Topic 1:ドラマの舞台となった当時の中国について
早速作品の考察に移りたいところですが、考察のためには、その材料についてある程度知っておく必要があります。まずはこの作品の背景、すなわち歴史的背景や、芥川の人となりについて確認していきたいと思います。
舞台は湖南省
さて、「STRANGER」の舞台の中心となっているのは中国・上海ですが、ストーリーの後半の舞台は、正確には上海の南西に位置する湖南省です。
芥川は上海を見聞した後、湖南省から長江を北上して北京まで視察をし、帰国しています。今回のドラマではその旅のうち、上海および湖南省の旅行記を取り上げているというわけです。
中国の旅行記は全体としては『支那游記』としてまとめられており、その中には『江南游記』、『長江游記』、『北京日記抄』などが含まれています。
「租界」という混沌
1920年代の中国・上海は欧米列強(イギリス、アメリカ、フランス)の租界、すなわち外国人居留地域として存在していました。

ちなみに、現在でも上海には「バンド」と呼ばれる地域が存在しています。高層ビルやタワーを一望できる河岸に近い旧外国人居留地エリアで、西洋風の建物が立ち並び、西洋文化がこの地域に大きな影響を与えていることが感じられます。

租界ができた経緯 社会情勢
さて、この租界ができた重要なきっかけが、アヘン戦争です。
当時イギリスは中国(清王朝)原産である茶や絹を、銀で買っていました。産業革命を経て綿織物を大量生産するようになると、その買い手であるインド産の麻薬、アヘンを中国(清)に売ることで、間接的に代金である銀を回収し、輸入過多を解消するシステム、いわゆる「三角貿易」を生み出しました。
清王朝は自国民がアヘン漬けにされるうえに銀まで奪われるため、英国と戦争を始めました。果たして、アヘン戦争に敗れた清国は1842年に南京条約を結び、上海を開港したのです。イギリス、嫌なヤツですね。

その後、弱体化が判明した清朝は西欧諸国から次々と開港を迫られ、不利な条件での貿易を行う半植民地のような状態になっていきました。
そこに目を付けた当時の新興国である日本は、日清戦争に勝利し、賠償金や朝鮮半島といった地域を清朝から奪いました。
西洋諸国に蹂躙された清朝は西洋化に踏み切ろうとしますが、混乱に乗じて各地で民族蜂起が次々と発生。清朝は、1911年の漢民族による辛亥革命によってついに滅亡しました。各地(15省)が次々と独立を宣言したため、中国国内は群雄割拠の混沌とした雰囲気になっていました。
たくさんの民族を抱えている大国にとって統治が非常に難しいのは、ここに理由があります。一つの民族が反乱を起こすと他の民族も同様に立ち上がってしまうのです。現在でもロシアや中国といった大国が少数民族の独立に厳しい態度を取らざるを得ないわけです。多数の平和を守るために少数を抑圧しているということなので、非常に繊細で難しい問題です。
中国文化に憧れていた芥川
「STRANGER」の映像の中でも、当時の雰囲気が再現されています。上海の西洋風の建物と庶民の暮らす掘っ立て小屋の共存している雰囲気や、アヘン窟の描写、治安の悪化、共産運動、抗日運動の様子は、ストーリーにも影響を与えています。
作品内でも述べられていますが、芥川は「西遊記」「水滸伝」「三国志」などといった中国古典のファンであることを公言しています。また、「杜子春」など中国の古典をモチーフにした作品を発表したり、漢詩のコレクターであったりと中国文化のことが大好きです。
雄大な世界観と豪快な人物たちが登場するこれらの作品のイメージから、大国としての歴史、政治、文化に敬意を持っていた芥川。しかし、1920年代の中国の文化は内外から破壊され、混沌とした状態でした。この状況を見た芥川が失望していたことは、「上海游記」の中でも繰り返し語られています。最も鮮烈に表している部分は作品でも取り上げられたこちらの部分です。
「政治、学問、経済、芸術、悉く堕落しているではないか? 」
期待していた分、好きであった分だけ、芥川の中の「かっこいい大国、中国像」が、明確に破壊されたわけです。(その一因はもちろん、日清戦争後にお金や領土を奪った日本なのですが……)
Topic 2:中国滞在がもたらした芥川の思想の変化
それでは、そんな芥川がどのようにこの激動の中国を見つめたか、というポイントに移ります。
芥川の物事への基本スタンス
「STRANGER」では、芥川の物事に対する基本スタンスが何度か示されています。冒頭のシーンでは、このように述べています。
「僕はどういう良心も持っていない 僕の持っているのは神経だけである」
芥川龍之介「歯車』から引用されたセリフ
一般的に、人間は一定の良悪の判断基準のもとに生きていると言えます。
例を挙げるならば、「物を盗むのはよくない」という判断基準のもと、窃盗・万引き事件に対して嫌悪感を持つわけです。
しかし、現象には様々な側面があるので、その良心が強すぎると「なぜ盗んだのか」などという別の側面に対しての視点を制限してしまう可能性があります。
芥川は作家ですので、小説という世の中で、複数の側面を持つ現象をそのまま描きたいと考えていたのではないでしょうか。
人間というものを描く際には、「良心=モラル」と共に、それを打ち破る人間の弱さ・もろさ・狡さなどといった側面も同時に描いたほうが魅力的なはずです。
そのために、物事を神経すなわち自分の感覚を使ってそのままとらえる、ということに重きを置いていたのだと思います。
中国の例に当てはめるとするのならば、インテリである芥川は、中国の状況に対して一定の知識をもって接していたはずです。しかし、それにとらわれずに、自分がどのように見たか、感じたかということに重きを置いて中国を見たのだと思います。
そんな基本スタンスに変化が
その後、物語の中で、芥川のこのスタンスが変化していることが示されます。
それは、中国共産党の発足に尽力した李人傑(本名:李漢俊)と会談した時のこと。
「僕はこちらに来てからというもの、どういうわけか政治のことばかり考えている、柄にもなく。」
という独白が語られます。
政治というのは極めて現実的なものです。様々な物事を決定していくための仕組みなので、物事を決定していくための一定の価値観、つまり「良心」を求められるのです。
日本では芸術を政治よりも重要と考えていた芥川ですが、中国の惨状、人々の困窮を見ているうちに、それらは現実を仕組みから変更する手段である政治でしか変わっていかない、という考え方になっているというわけです。
これは、中国に対して憧れを持っていた芥川の中にあった部分が、作家としてではなく個人的な理由のもと、芥川らしくなく、極めて感情的な形で現れた場面だと思います。
あるいはこの作品の中で、淡泊で物質主義・合理主義的だった芥川が中国の現状に触れることによって、自らの中にある情熱的で革命的(プロレタリア的)な考え方に気が付かされるという変化がある、と言えるでしょう。
実際に、帰国後の芥川の作風には、労働者らの変革であるプロレタリア主義の影響が多く見られます。
著作「桃太郎」では、日本の帝国主義を寓話の桃太郎に見立て、「鬼の平和な生活を破壊する行為は侵略だったのではないか」と批判しています。また、「将軍」では、指揮者の無謀な作戦によって無下に死んでいく兵士たちの様子が描かれています。この指揮者は、検閲により伏字にはなっているものの、天皇や、陸軍の将軍であった乃木希典ではないかと推測されます。
これらの作風の変化は、政治に首を突っ込みたくないという態度をとっていた芥川にとっては大きな変化と言えます。
日本という国が戦争に向かっていく時代に、このように考えていたということは、戦争に負けた側である中国を精緻に見つめた結果と考えると、理にかなっていると思われます。
次回に乞うご期待!
なんだか暗い話になってしまいましたが。
混沌とした中国、そして戦争に向かって高揚していく日本は当時、物々しい雰囲気だったのだと思います。
人々の不満や貧困と、それを覆いつくそうとする政治的思想、イデオロギーが、様々な立場から沸き上がり、ぶつかり合っていた熱量の高い時代。その中を、芥川は生きていたわけです。
その物々しさに神経をすり減らし体調を崩しながらも真正面から描こうとした芥川という作家は、やはり器の大きな作家だったと言えるのではないでしょうか。
それでは、物語の世界をご紹介する初回のコラムはここまで。次回、またお会いしましょう!
参考リンク
次回のコラムはこちらから↓
劇団のので朗読した芥川龍之介の作品はこちらから↓
ドラマについてNHKのサイトはこちら↓