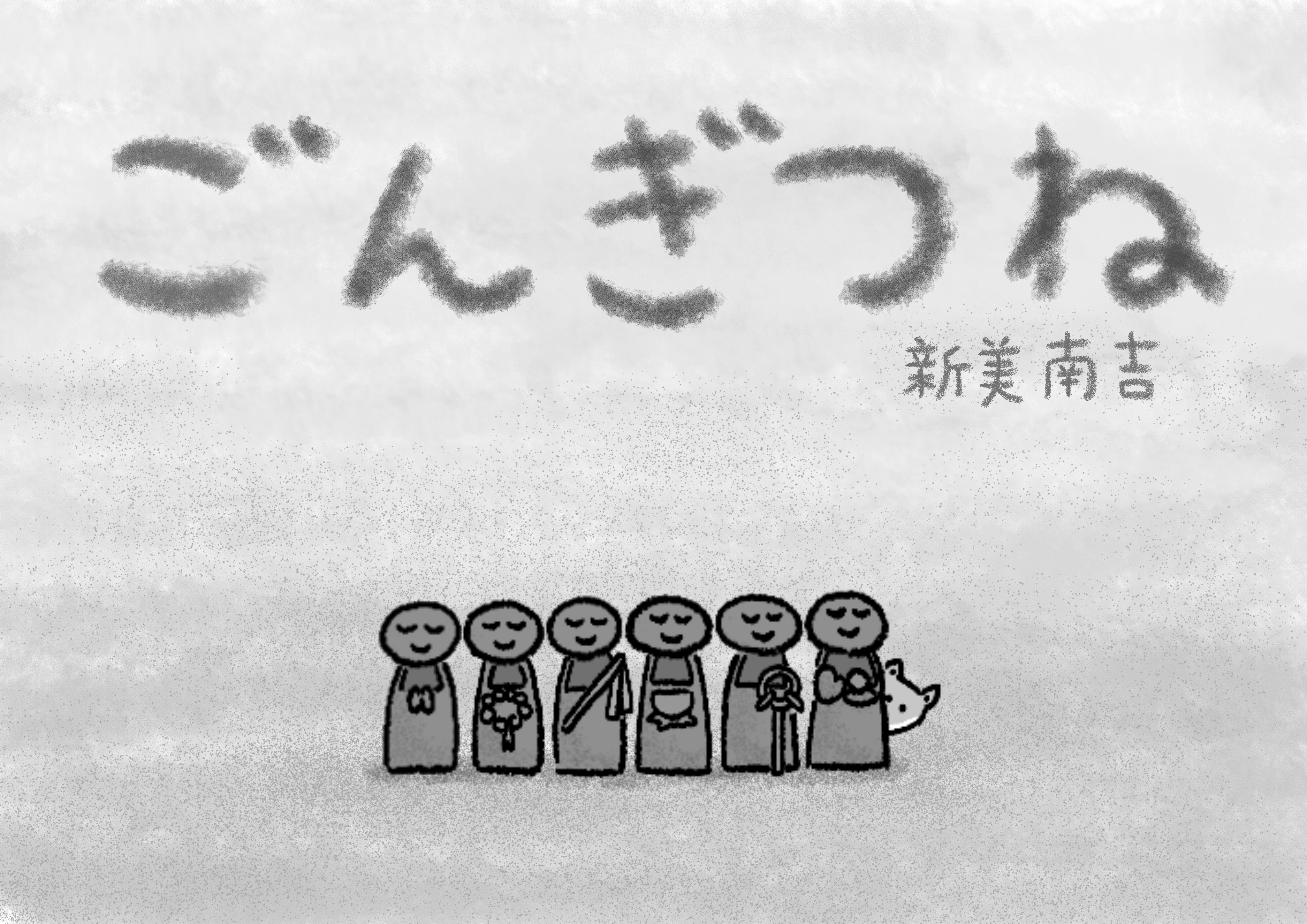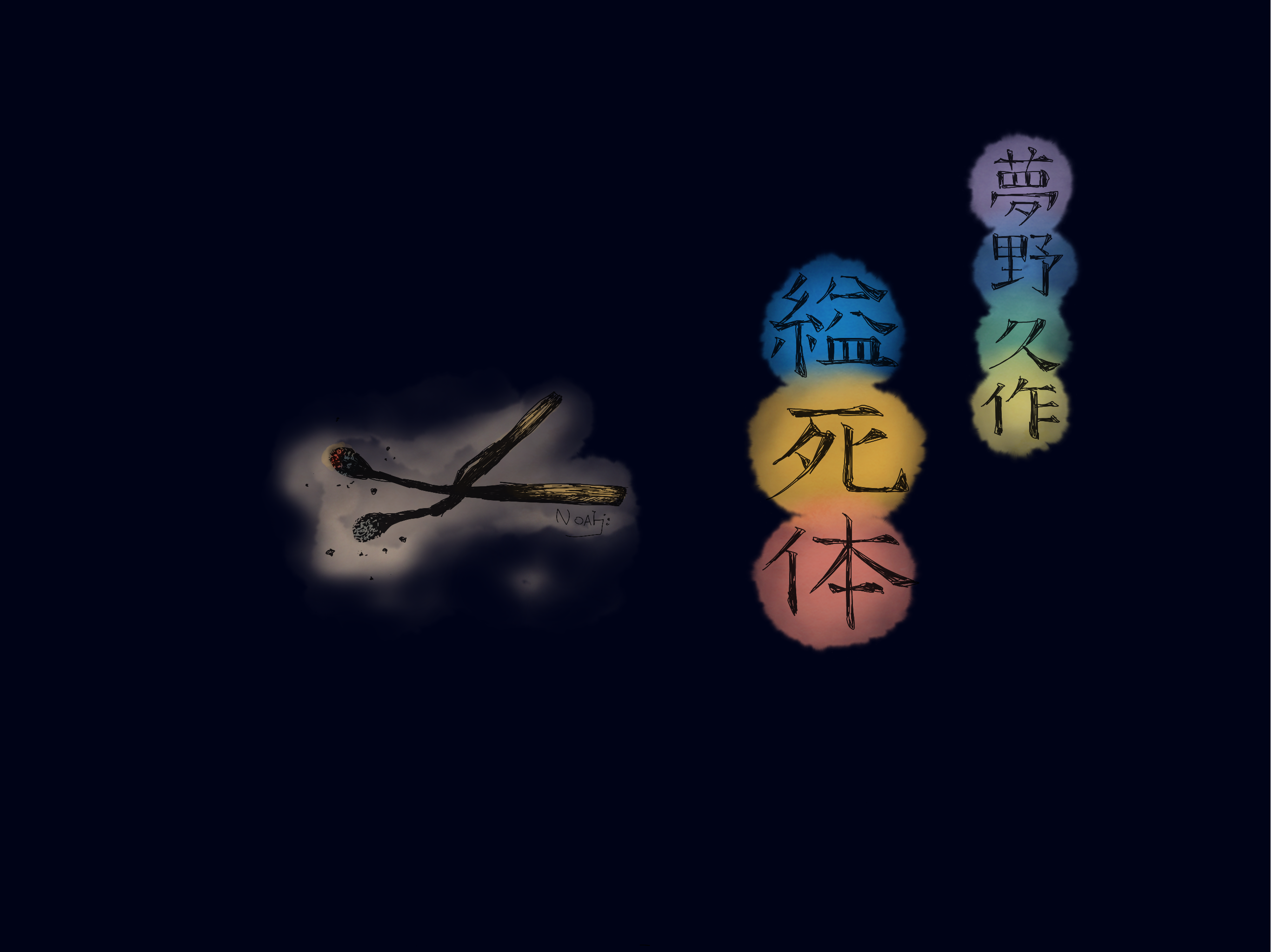新美南吉の短編『ごんぎつね』に登場する、ちょっと難しい言葉の意味を調べてみました。
劇団ののは、言語学や歴史学のプロフェッショナルではありません。
様々な文献や辞書をあたったり、プロフェッショナルの方に手助けをいただいたりはしていますが、あくまでも自力で調べ物をした結果を掲載しています。誤った情報が含まれている場合がありますので、ご注意ください。
また、調べ物をした結果、真実が突き止められないこともあります。
ご了承ください。
- 中山・中山さま【なかやま】
- しだ
- 一ぱい【いっぱい】
- 菜種がら【なたねがら】
- 百姓家【ひゃくしょうや】
- 百舌鳥【もず】
- つつみ
- はりきり
- びく
- お百姓【おひゃくしょう】
- おはぐろ
- 鍛冶屋【かじや】
- 髪をすいて【かみをすいて】
- お宮にのぼり【おみやにのぼり】
- 六地蔵さん【ろくじぞうさん】
- 白いかみしも【しろいかみしも】
- 位牌【いはい】
- 床についていて【とこについていて】
- ちょッ
- 赤い井戸【あかいいど】
- 麦をといで【むぎをといで】
- 盗人【ぬすっと】
- 木魚【もくぎょ】
- お念仏【おねんぶつ】
- かげぼうし
- 思わっしゃって【おもわっしゃって】
- 俺は引き合わないなぁ【おれはひきあわないなぁ】
- 縄をなって【なわをなって】
- 火なわじゅう【ひなわじゅう】
- 青い煙【あおいけむり】
- 参考文献
ごんぎつねには、新美南吉が執筆した原稿に、当時、児童文学雑誌『赤い鳥』の編集者であった鈴木三重吉が多分に手を加えて、誰もが知る今の形になったという経緯があります。
この記事では、改編前に書かれていた単語についても言及します。
中山・中山さま【なかやま】
戦国時代、新美南吉の地元(岩滑)に実在していたお殿様(中山勝時)がいます。
その後、中山家はいくつかの系統に分かれて、江戸時代には徳川家などにも仕えます。
新美の元の原稿には「むかし、徳川様が世をお治めになっていられた頃に、中山に、小さなお城があって、中山様というお殿さまが、少しの家来と住んでいられました」とあり、ごんぎつねは江戸時代という時代設定になっています。
これはかつての領に戻って来ていた子孫のことかもしれません(正確には、中山氏が中山城でお殿様だったのは戦国時代のこと)。
鈴木版では徳川の名は削られて時代がぼかされていますが、これには、当時「天皇陛下のもとで一丸となる」という考え方が重視されていたという事情が関係しているという説があります。(参考:沢田保彦『南吉の遺した宝物』2013)
南吉は、中山氏の末裔と家族ぐるみで親しくしていました。南吉は、中山家の娘である「ちゑ」と友人であり、思いを寄せていました。また、その母「しゑ」から民話を聞かされていたことが、南吉の童話のルーツであるとする説もあります。
中山城があった辺りには、現在、新美南吉記念館があります。
しだ
シダ植物の総称で、様々な種類があります。
日陰や湿気のあるところを好みます。都会でも、裏庭や玄関周り、室外機の周りなど、比較的日当たりのないところで見かけることができます。
観葉植物として育てられることもあります。
鈴木版では「その中山から、少しはなれた山の中に、「ごんぎつね」というきつねがいました。ごんは、ひとりぼっちの小ぎつねで、しだのいっぱい茂った森の中に穴をほって住んでいました。」とありますが、実際のホンドギツネは草原や比較的日当たりの良い場所に巣を持つのが一般的であり、シダが生い茂る湿気の多い場所というのは、やや違和感があります。

新美版には「その頃、中山から少し離れた山の中に、権狐という狐がいました。権狐は、一人ぼっちの小さな狐で、いささぎの一ぱい茂った所に、洞を作って、その中に住んでいました。」とあり、シダではなく「いささぎ」という植物が示されています。
これはこの地域の方言で、ヒサカキ(姫榊)という、お供物などに使用される植物のことをさすようです。

新美南吉記念館のあるところからは、矢勝川を挟んで権現山が臨めるため、「権現山付近に住む権ぎつね」と考えるのが自然でしょう。(諸説あります。)
一ぱい【いっぱい】
ここでは、「たくさん」という意味で「いっぱい」です。
菜種がら【なたねがら】
菜種は、アブラナの種で、これをしぼって油をとります。
菜種がらは、この種を取り去った後の茎などの部分です。干して乾燥させ、火を起こす際に使用されたりしました。(今でも薪や炭に火をつける前に、マッチで新聞紙などに火をつけてから、その炎を移しますね、そのような使い方をされていました。)
参考:ごんぎつねがいたころ
百姓家【ひゃくしょうや】
農家の家屋のことです。
百舌鳥【もず】
全長20cm程度の肉食の鳥です。
「モズのはやにえ」といい、捕まえた小さいトカゲやカエルなどを尖った枝などに突き刺しておくという不思議な習性を持っています。
つつみ
河川や池・湖などの水辺にある、水が溢れないように高く盛られた部分のことです。
堤防の「堤」と書いて「つつみ」と読みます。
土でできているものは「土手」と呼ばれますが、石垣やコンクリートでできていることもあります。
はりきり
川に張っておいて、魚を捕まえるための網です。
川を横断して魚の通り道を塞ぐように張るため、南吉の地元の岩滑(やなべ)では「張り切り網」と呼ばれていたようです。
この物語が掲載される際、編集者の鈴木三重吉がずいぶんと原稿に手を入れ、他の方言や子どもが理解しづらい単語はいろいろと直されていますが、この言葉はそのままにされています。
新美南吉記念館の天井には、大きなはりきりがぶら下がるように展示されています。
びく
捕った魚を入れておく、竹でできた壺型のかごです。
腰にぶら下げたり、地面に置いたりしていました。
新美南吉記念館では、びくに手をかける小狐の剥製が展示されています。
お百姓【おひゃくしょう】
農家、農民など農業に従事する者のことです。
ただし、「都会の趣を理解しない田舎者」など侮蔑の意を込めて使用された経緯から、現代では差別語に類することもあります。
おはぐろ
歯を黒く染めることから「おはぐろ」と言います。
日本に昔から存在する風習で、時代によって男性・女性、皇族貴族・一般人など、おはぐろを行う立場は変遷します。
江戸時代以降には既婚女性が、鉄などの染め粉を使って行うのが一般的でした。
ムラなく真っ黒く光っているのが、とても美しく魅力的に感じられたようです。
ごんが通りかかった時には、染め直しのメンテナンスをしていたものと考えられるでしょう。
昭和の頃には見られなくなりました。(司馬遼太郎の小説にはご自身がおはぐろしている女性に会ったという記述がありますが、本当かどうかは分かりません。)
鍛冶屋【かじや】
鉄製の農具、馬具、刃物、工具などを作る、または修理する職人のことです。
熱した鉄をハンマーで整形するなど、製作工程は様々です。
髪をすいて【かみをすいて】
現代では、「髪をすく」というのは、散髪の際、ハサミを滑らせるようにして、全体的な毛量を(先細らせるように)減らすことを表しています。
しかし、ここでは、髪を櫛でとかすことを表しています。
漢字では「梳く」と書きます。
お宮にのぼり【おみやにのぼり】
神社に、竿についた細長い布の旗が立てられる様子を表しています。
ごんは、よそいきの準備をしたり、料理を作る女性たちを目にしつつ、「これがお祭りの準備であれば神社にのぼりが立つはずだから、そうではない」と推理しています。

六地蔵さん【ろくじぞうさん】
お地蔵さまは、仏教の世界において、高い徳を積んだ「菩薩」であり、正しくは「地蔵菩薩」という存在です。
仏教では、生前の行いに合わせて、生まれ変わる先の選択肢として、6つの死後の世界があると考えられています。良い順番に、天上界・人間界・修羅界・餓鬼界・畜生界・地獄です。仏教の修行を重ね、悟りを開かなければ、生まれ変わる度にこの世界を回る「輪廻・転生」から抜け出すことができません。
6つのお地蔵様は、それら6つの世界に合わせて、(「衆生救済」といい)悩み苦しむ者たちを悟りへと導くためにいます。
菩薩や輪廻については、以下の記事をご参照ください。
白いかみしも【しろいかみしも】
通常の袖のある着物の上から身につける袖のない上着と、袴の組み合わせです。
現代のイメージでいうと、ベストやジレと呼ばれるものに近い形でしょう。
江戸時代には武士の平服や礼服(スーツのような存在)となります。
やがて、農民や町民も冠婚葬祭など重要な場に身に付けることがありました。
現代でも、例えば能や歌舞伎など伝統芸能の舞台や、祭事などで使用されています。
日本で喪服が主に黒いものとされるようになったのは、明治時代以降、西洋文化が流入した後のようで、それ以前は白が多用されていました。
(参考:白い時もあった喪服。喪服が黒い理由とは?)

位牌【いはい】
仏教において、死者のために、戒名などを記した木の板です。
起源や歴史的経緯については複数の宗教などが関係しています。
日本には鎌倉時代に伝来して、江戸時代に広く一般化しました。

床についていて【とこについていて】
寝床(布団やベッドなど)に横たわっていることをいいます。
ただ眠るために横になることをいうこともありますが、ここでは、兵十の母親が病や衰弱などで、ほぼ寝たきりになっていること、すなわち病床にあることを表しています。
新美版では「床にふせっていて」と書かれています。
ちょッ
舌打ちの音です。
現代では「ちぇっ」と表現する方が一般的でしょう。
(とはいえ、漫画やアニメなどでは頻繁に見かけますが、実際に「ちぇっ」と言う人はあまり見かけなくなりましたね。)
赤い井戸【あかいいど】
この地域の土は、いわゆる赤土という、赤茶けた土でした。
付近の常滑では、この赤土を使った焼き物が有名です。
麦をといで【むぎをといで】
麦を食べる時も、白米と同じようにといで洗う必要があります。
兵十は裕福ではないため、米ではなく、麦などの雑穀を食べていたかもしれません。現代では、雑穀米は健康的でおしゃれな食べ物として好まれていますが、昭和の中頃までは、白米が贅沢品であり、他はその代替品のように思われていました。
(参考:結局「麦(大麦、もち麦、はだか麦、押麦)」はお米と同じように洗うの?洗わないの?(完結編))
盗人【ぬすっと】
泥棒(どろぼう)と同じです。
木魚【もくぎょ】
木製で、魚の模様が彫られています。
中が空洞になっていて、バチで叩くと、ポクポクと音が響きます。
仏具で、お経を唱える際にリズムを取りながら叩くものです。
ちなみに、新美版では木魚の音は「モク、モクモク、モクモク」という風に書かれていて、たしかに、障子越しであれば、その方が実態に近いのかもしれません。

お念仏【おねんぶつ】
本来、「念仏」とは、仏のことを思い浮かべたり、その名を唱えたり、称えたり、感謝を口にしたりすることをさしています。例えば「南無阿弥陀仏」と唱えることを「念仏を唱える」と表現することがあります。
一方、仏典にしっかり記されている「お経」というものを読み上げることは、読経といいます。
ここでごんが言う「お念仏があるんだな」は、障子の向こうに見えているお坊さんがお経を唱えることをさしていると考えて良いでしょう。
この場合は、広く、法要そのものをさしているかもしれません。
かげぼうし
影のことです。
「ぼうし」は「一寸法師」などと同じで、お坊さんや人間のことを表す言葉です。
人間と一緒について回るお伴のような存在に対する、愛称のようなものでしょう。
思わっしゃって【おもわっしゃって】
「しゃる」は「なさる」と同様の尊敬語です。
ここでは「お思いなさって」といった意味です。
歌舞伎のセリフなどでは「おむしゃる」「ござしゃる」などという言葉遣いが残っています。
博多弁にある「行きんしゃる」「おりんしゃる」も同様の名残でしょうか? 定かではありません。
ちなみに新美版では単に「思って」とされています。
俺は引き合わないなぁ【おれはひきあわないなぁ】
何かを引き受けて、その見返りが割りに合わないという意味です。
ここは、新美版では「神様にお礼を言うなんて、いっそ神様がなけりゃいいのに。権狐は神様がうらめしくなりました。」となっており、「引き合わない」は鈴木が新しく加えた言葉です。
「神様がいなければいい」「神様がうらめしい」という、神様を否定する直接的な表現は、子ども向けの作品として教育によろしくないため、削除されたのでしょうか。
縄をなって【なわをなって】
漢字では「綯う」と書きます。
糸・藁・紐などを撚(よ)り合わせて、1本の太い縄にすることをさします。
多くの場合、床の上に座り、縄の端を両足の裏や足の親指と人差し指で挟み、両手に挟んだ縄をこすり合わせるようにして、ねじりながら太くしてゆきます。
YouTubeの動画などで、職人さんが藁(わら)を使って縄をなう様子を見ることができます。
(参考:秋田県立博物館「縄を綯う」)
火なわじゅう【ひなわじゅう】
火縄銃は古くからある鉄砲の種類の一つです。
15世紀頃にヨーロッパで開発され、日本にも徐々に伝来して、戦・狩猟に使用され、普及しました。
弾丸と黒色火薬を銃口から奥に向かって入れます。火のついた火縄を、火ばさみという部分に挟んでおきます。引き金を引くと、バネで火ばさみがはじかれ、火皿に打ち付けられます。火皿から内部に着火して、弾を発射します。
ちなみに、何か争いや戦いが始まる際に「火蓋が切られた」という慣用句を使用しますが、これは火縄銃の一部分である火蓋を開いて点火準備をすることから、このように言われています。
江戸時代にはあまり戦がありませんでしたが、幕末の頃に再び多用されました。この頃、欧米から進歩した別の種類の銃が流入し、あまり使用されなくなっていきます。
(参考:刀剣ワールド「火縄銃とは」)

青い煙【あおいけむり】
この「青いけむりが、まだつつ口から細く出ていました」という最後の一文は、「ごん、お前だったのか」と同じくらい、ごんぎつねの物語の中で有名な文です。
しかし、実際の黒色火薬の煙は、一般的には白色であるようです。新美はここであえて「青い」と表現しています。
ややグレーががったような白を、赤みが足りない硬く冷ややかな「蒼(あお)」という意味で「青」としたのかもしれません。また、兵十の納屋の赤土の土間に取り落とした火縄銃ですから、床の赤茶けた色を背景とした煙は、対比によって青々とした印象を持ったのかもしれません。
明確な答えはありませんが、それも含めて、人々の心に深く残る一文となったのでしょう。
仮にこの部分を「白いけむり」としていたら、ここまで我々の記憶に残らなかったかもしれませんね。