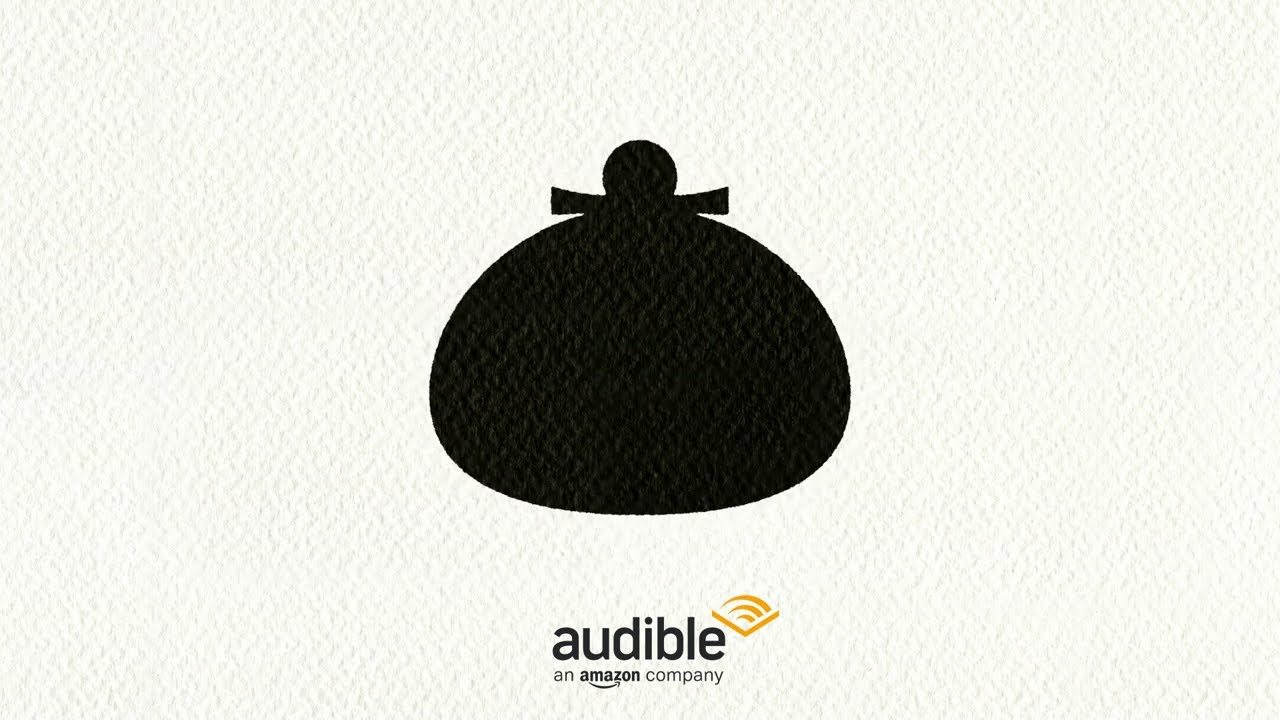みなさま、いい朗読ライフ、お過ごしですか?
劇団のの 水色担当の栗田ばね です。
今回のブログは【勝手にアーカイブ】シリーズ まさかの第2弾。
現在発売中『本の雑誌』2025年10月号の「特集 本は聴くもの!?」を
”勝手に”ふりかえらせてもらいます!
あくまで書評の一環・・・!ということで。ご海容願います。
近頃にわかに世間に広まったように思われる、オーディオブック界隈。
その特集を、あの『本の雑誌』が!
これは見逃せませんよー。
『本の雑誌』とは
が、ちょっと足踏みして「本の雑誌」のご紹介を。知ってる人はしっている、知らない人はしらない時代ですものね。
まるで一般名詞みたいですが、本に関することを扱う雑誌なんです(同語反復?)。
つまり、書評・ブックガイドを基本に、色んな企画もある雑誌。
創刊メンバーのひとりは、あの小説家・世界各地に行く人、椎名誠さん!
当時(創刊1976年)の書評・本の紹介といえば、新聞に大学教授などが書く、学術的…文学的…難しい的なものが多かったそうで。
そーゆーふーなのじゃなくて、もっと面白い本を知りたいんだよなァー、
というようなふーに、開始された雑誌なのです。
また別の創刊メンバー:目黒孝二(書評での名義は北上次郎)さんのおなじみフレーズは
「いやはや、すごいぞ、ぶっとぶぞ」
本を読んで面白かった! を共有してくれる雑誌。現在は「本屋大賞」の運営にも関わっています。
そんな本の雑誌、2025年10月号の特集が「本は聴くもの⁉」。すなわちオーディオブックについてでした。
閑話休題。本題。
特集「本は聴くもの⁉」 ①Amazonオーディブル担当インタビュー
まず巻頭は「Amazonオーディブル」担当者の方(キーリング・宮川もとみ さん)へのインタビュー。
なんでも年々オーディブルのリリース数は増えており、2025年は前年比40%越えの見込みとか。すごい。
本の出版よりも朗読作品が先な「オーディオファースト」作品も製作されているそうで、
2021年の川上未映子さん『春の怖いもの』が第一作。
これは作家さんが朗読作品用に書いているので、テーマから文章のリズムまで朗読用になっているとか・・・聴いてみたい!
また制作環境の話では、
収録に際しては書籍のままではなく必ず台本を作り、ナレーター・スタッフ皆おなじものを見て進める、とか、
収録・編集後は複数人が聴いてチェックし、読み間違い等のリテイクの日程を必ず設けている、とか・・。
最近の音声合成技術も採り入れていて、黒柳徹子さんの『続 窓ぎわのトットちゃん』は、第一章だけご本人。以降は合成音声(デジタルナレーション)なのだそうな。
こちらで、デジタルナレーションのごあいさつが聴けます!
②「オーディオブック担当者座談会 聴く本と読む本で体験がひろがるのだ!」
次に制作事情を聞けるのが、こちらの座談会。出演は小学館、新潮社、早川書房の方たちです。
まず前提となるのが「原盤権」の存在。作品音源の権利、ですね。
たとえばオーディブルから話が来て、音源を作ってもらったら、制作費はもたなくていいけれど原盤権がオーディブルに帰属する。だからオーディブル以外のストアには出せなくなってしまう・・。
ハヤカワは「三年くらい前から」自社制作(=自社で発注する)を始めたそうで、小学館は原盤権を持つケースは半々くらい、新潮社は自社制作はおこなっていないそう。
原盤権をもっていれば色んなオーディオブックストアに出せる、反面、制作の初期費用回収に時間がかかる・・。
と悩ましさの反面、2024年のヒット作『成瀬は天下を取りにいく』は、「Amazon Audible」と「audiobook.jp」(会社名:オトバンク)の両方に作ってもらったそうで、
制作陣の違いによって、同じ本もオーディオブックではこんなに変わる! という楽しみも。
かんたんにわけると、オーディブルはスピード感のある体制で、芥川賞・直木賞などはノミネートされたらすぐ作り始め、受賞発表からすぐリリースすることも多い。朗読は一人ナレーションが多い。
オトバンクは、ラジオドラマ的に複数キャストで、効果音・BGMも入れてじっくり制作することも多い。とのこと。
(劇団ののも、オトバンクさんのパターンが多いですねえ~)
本をよく読む方には、ドラマ的な音源よりもひとり朗読の方が、読んでる感覚に近くていいという意見があるみたいです。むずかしいなあ。
『十二国記』(オーディブルとオトバンク両方で制作中)では、著者から、1冊をひとりナレーターで読むようにしてほしいと要望があったとか。でも効果音・BGMはOKだったとのこと。これも面白いご意見ですよね。
そして、この条件でも、やっぱり二社の音源は色の違ったものになっているそうで。
必聴です!
朗読の収録には、出来上がり音源のおよそ3倍の時間がかかるのだそうです。長篇では何十時間、何日もかけて読み、複数人のチェックが入り、さらに修正の収録をする・・。
「チェックするのは気が遠くなるような作業です。我々にも限界がある(笑)」
とは、ハヤカワ担当さんの弁。対して新潮社は・・
「うちは担当者が全部聴いて、一作品につき多い時は二十か所以上の指摘があります」
新潮社の校閲は、オーディオブックにも厳しかった!
ちなみに海外の書籍だと、複数人朗読=ラジオドラマ=CDドラマ的なものは、オーディオブックとは違う契約になるそうです。これも面白い~。
音質ってなんだろう・・
余談ですが、栗田としては「どうしてオーディブルの音質はああなのか・・?」ということを誰かに訊いてほしかったんです・・でも、両記事ともその言及はなく。
オーディブル利用に踏み切れないのが、あの”前時代の圧縮技術”って感じの音なんですよね。シュワッ、シャ、ワララン、みたいな音成分が頻出する、あの圧縮感。
長時間データ通信することを前提にするから、仕方ないのかもしれませんが・・。
でももしかしたら、そういう「人の声の生々しい成分」を一部カットしてしまうその感じ、も、
「本の文面を音で聞いている」ことに通じるのかも?
ののラジオを作ってきて「もっと音良くならんかなァ~」としょっちゅう思ってきた身には、あれあれ、ですが、ラジオドラマじゃなくて「本の音化」だとすれば、あの音質も指向性に合っているのかも・・!
う~ん。悩ましい所です。
まだまだすごい記事がのっているぞ!
さてさて、他にも「私のおすすめオーディオブックベスト3!」という記事や、
ジョギング・ウォーキングしながら聴く(CMの通りだ!)オーディオブック、
読み聞かせとオーディオブック(「サピエ図書館」という、障碍者むけのデータベースがあると初めて知りました。音訳図書)、
それに
オーディオブック朗読といえば(?)の、池澤春菜さんのエッセイ。
『アルジャーノンに花束を』の、チャーリイが変わっていくさまをあらわした朗読は賞賛の嵐ですぞ。
バックナンバーをどうぞ
というわけで『本の雑誌』。まもなく11月号が発売です!
バックナンバーの注文もかんたんにできると思いますので、気になった方はぜひご購入を!
今回はふれられませんでしたが、連載も もちろん!おもしろいですよー。